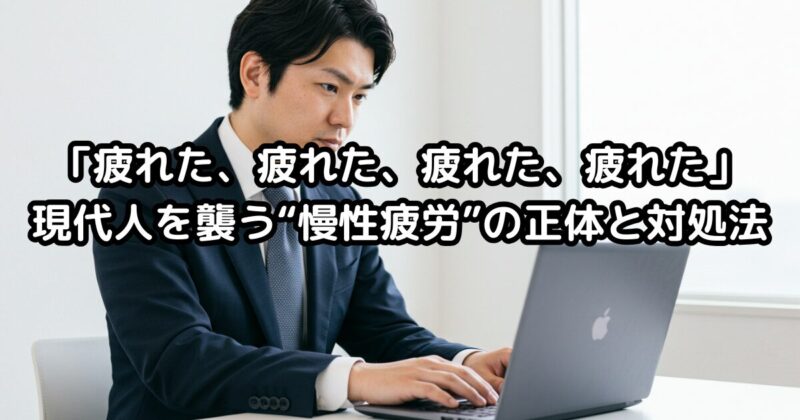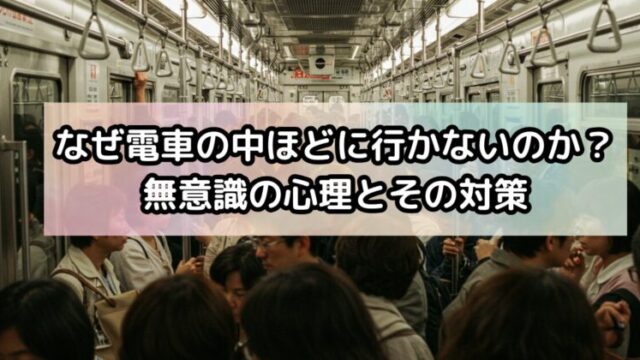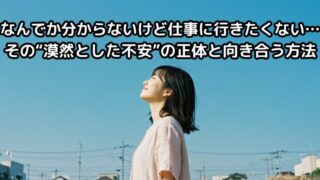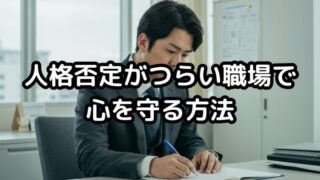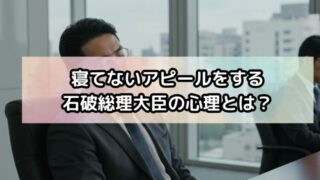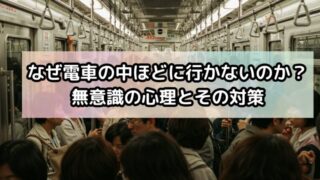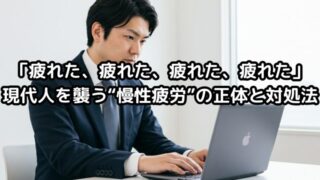1. 疲れているのに、なぜか休めない私たち
1-1. 身に覚えのある“疲れのループ”
朝起きた瞬間から「疲れた」が口ぐせ
朝起きてすぐ「はあ…疲れた」って、つい口から出たこと、ありませんか?私はしょっちゅうです。何なら寝る前からすでに「明日も疲れてるんだろうなあ」なんて思っちゃってます。
たっぷり寝たはずなのに体が重くて、顔を洗ってもスッキリしない。コーヒーを飲んでも目が覚めない。そんな朝が続くと、1日の始まりからすでに心が折れそうになりますよね。
これ、私だけじゃなく、周りの同僚も同じこと言ってるんです。寝ても取れない疲れ。もはや「疲れてるのが普通」みたいな感覚になっていて、ちょっと怖くなります。
疲れてる理由が思い当たらないのに、常にエネルギー切れ。これって単なる「寝不足」じゃない気がするんですよね。
週末に休んでも月曜にはまた「疲れた」
土日にしっかり休んだつもりなのに、月曜の朝にはまた「疲れた…」が始まる。正直、何のための休日だったんだろう?って思ってしまうこともあります。
私も最近、金曜の夜に「今週もやりきったー!」って思っても、日曜の夕方には「明日からまた仕事か…」って気持ちがどんよりしてしまいます。
一応リフレッシュしたはずなのに、月曜になると元どおり。まるで充電したはずのスマホが朝にはもう残量20%になってるみたいな感覚。そんなこと、ありませんか?
「疲れた」と言うたびに心までどんより
そして怖いのが、「疲れた」って言葉そのものが、気分をどんどん沈めていくこと。
口グセみたいに「疲れた〜」って言っちゃうんですけど、言えば言うほど自分に暗示をかけてるみたいで、余計しんどくなるんですよね。
それに、「疲れた」って言うだけで、なんかもう行動する気も起きなくなっちゃう。不思議なことに、元気なときにはあまり言わないのに、言い始めると止まらないんですよ。
言葉って力があるんだなあとつくづく思います。「疲れた」を言わないように意識すると、少し気持ちが楽になることもあるんですけど、それでもやっぱり言いたくなる。だって本当に疲れてるんだもん。
1-2. その疲れ、実は“慢性化”しているかも?
単なる運動不足では説明できない疲労感
昔は「疲れたら寝れば治る」ってよく言われました。でも今の疲れって、寝ても治らないんですよね。これ、ただの運動不足とか年齢のせいじゃない気がします。
私もジムに通ってみたことがあるんですが、体を動かしたら余計に疲れたなんてことも…。つまり、問題は筋肉だけじゃなくて、脳の疲れや感情の疲れも関係してるんだと思うんです。
現代人は“疲労感”と共に生きている
今の時代って、常にスマホやパソコンから情報が飛び込んできて、気づいたら何かに追われてる感覚ありませんか?ニュース、SNS、メール…。頭が休まる暇がない。
しかも、職場でも家でも「ちゃんとやらなきゃ」と気を張り続けて、気がつけばヘトヘト。これってもう、疲労感が標準装備になってる感じですよね。
休んでも取れないのは根本が違うから
「休めば回復するはずの疲れ」が、どうしても取れない…。その理由は、根本的に“疲れ”の正体が昔とは違ってきているからじゃないかと思います。
例えば、頭の中がずっとフル回転しているとか、感情の起伏が多すぎて心が疲れてしまうとか。そういう目に見えない疲れが、私たちのエネルギーをじわじわ削ってるんですよね。
だから、ただ寝たり休んだりするだけではリセットできない。「疲れた、疲れた、疲れた、疲れた」って思ってしまうのも、実は“現代的な疲れ”に体も心も巻き込まれているサインかもしれません。
2. 現代人の“疲労”を解き明かす
2-1. 説明:疲労には「肉体」と「精神」の2種類がある
筋肉の疲れ=運動や労働によるもの
まず分かりやすいのが、「筋肉の疲れ」ですね。これは、たとえば重たい荷物を運んだり、通勤で長時間歩いたりしたときに感じる、いわゆる“身体的疲労”です。
私も昔、引っ越しの手伝いで1日中動きっぱなしだった日は、夜には全身バキバキ。でも、ぐっすり眠れば翌朝にはスッキリしていた記憶があります。
このタイプの疲れは、原因がはっきりしているし、基本的には一過性。ちゃんと休めば回復するのが特徴です。
でも、最近感じる疲れって、そういう単純なものじゃない気がするんですよね…。
脳の疲れ=情報過多やマルチタスク
今の私たちが抱えている疲れの多くは、「脳の疲れ」じゃないかと思います。
スマホ、パソコン、タブレット…とにかく情報のシャワーを浴び続けている毎日。朝からメールチェック、日中は会議でフル回転、夜になってもSNSで頭が休まらない。
私も仕事中に複数のタスクを同時進行することが多いんですが、正直、何が終わって何が途中なのか、脳が処理しきれていない感覚があります。
こういうマルチタスクが脳に大きな負荷をかけて、気づかぬうちに脳疲労をためこんでしまうんですよね。
感情の疲れ=人間関係やSNSの影響
さらに最近感じるのが、「感情の疲れ」。これがかなり厄介なんです。
仕事の人間関係、家庭での役割、SNSでの“いいね”の数。知らず知らずのうちに、他人の評価や目線を気にしてしまう。自分でも気づかないレベルで、心がすり減ってるんですよね。
たとえばSNS。何気なく誰かの投稿を見て「この人、すごいな…」と比べてしまったり、自分の投稿に反応がないとモヤモヤしたり。
これ、意外と大きなストレスになっていて、感情が疲れ切る原因なんです。
「疲れた」と感じるとき、必ずしも体が原因とは限らない。今は心と脳も疲れているという前提で、自分の状態を見直すことが大事だなと思います。
2-2. なぜ、こんなにも疲れやすくなったのか
スマホ利用時間の増加が脳を消耗させる
気づけばスマホを手にしてる。それ、私もです。
総務省のデータによると、日本人のスマホ利用時間は1日平均4.5時間を超えているそうです。朝の電車内から、仕事の合間、寝る直前まで、ずーっとスマホ。
私自身も寝る前に「ちょっとだけSNS見よう」と思って、気づいたら1時間…。しかも見てる内容は、人の近況とか、ニュースとか、自分に直接関係ない情報ばかり。
この“情報過多”の状態が、脳にかなりのダメージを与えているそうです。
脳は情報を処理し続けることで、エネルギーを消耗します。そして処理しきれない情報は“ストレス”として蓄積されていく。つまり、スマホを見れば見るほど、脳が疲れていくんです。
睡眠の質低下が回復力を奪っている
「寝てるはずなのに疲れが取れない」って方、多いと思います。
厚労省の調査では、約4割の人が「睡眠の質に不満がある」と回答しているそうです。これは思っている以上に深刻な話。
私も以前は寝つきが悪くて、夜中に何度も目が覚めることがありました。朝起きても、寝た気がしない。こんな日が続くと、回復どころか、疲労がどんどん蓄積されていきます。
質のいい睡眠がとれないと、脳も身体もリセットされません。特に深い眠り(ノンレム睡眠)が不足すると、回復力が激減するらしいんです。
「ちゃんと寝た」はずなのに「全然スッキリしない」…これこそ、現代人特有の悩みですよね。
運動不足が血流を悪化させ疲労を蓄積
「動かないと疲れやすくなるよ」と言われても、忙しい毎日で運動する時間なんて…って思いませんか?正直、私もそうでした。
でも、WHOのデータによると、成人の約25%が“運動不足”の状態なんですって。そりゃ疲れもたまりますよね。
運動不足になると、血流が悪くなり、酸素や栄養が全身に行き届かなくなります。結果、疲労物質が体内にたまりやすくなるそうです。
私もデスクワーク中心の生活を続けていた頃、ずっと肩こりとだるさが抜けませんでした。でも、意識的に体を動かすようにしてから、少しずつ体が軽くなったんです。
「疲れてるから運動できない」のではなく、運動しないから疲れが取れない。この発想の転換、大事かもしれません。
2-3. 根本的に“疲れない体と心”を作るには
スマホ時間の“制限ルール”を決める
スマホ疲れ、なんとかしたいですよね。私が最近試しているのは、「夜21時以降はスマホを見ない」ルール。
慶應大学の調査によると、1日30分スマホ時間を減らすだけで脳疲労が軽減されるという結果もあるそうです。
夜はスマホを充電器に置いたら手を触れないようにする。ベッドには持ち込まない。最初はムズムズしましたが、慣れると逆に気持ちが落ち着くんです。
この「意図的なスマホオフ」、かなり効果ありますよ。
「深い睡眠」を促す環境を整える
質の良い睡眠って、ほんのちょっとの工夫で変わるんですよね。
私が実践しているのは、「寝る1時間前にお風呂に入る」こと。ぬるめのお湯にゆっくり浸かると、副交感神経が優位になって、体も心もリラックスできます。
あとは、寝室の照明を暖色系にしたり、アロマを焚いたり、スマホを遠ざけたり…。ちょっとした環境の見直しで、眠りの深さが変わる実感があります。
「眠れない」じゃなくて、「眠れる環境をつくる」。それが疲労回復の第一歩だと思います。
毎日10分の散歩が“疲れにくい体”を作る
がっつり運動しなくてもいいんです。私が効果を感じたのは、1日10分の散歩。
東京都健康長寿医療センターも、「毎日10分歩くだけで疲労感が軽減される」と推奨しているそうです。
私も昼休みに会社の周りをグルっと歩くだけでも、午後の集中力が全然違いました。しかも、外の空気を吸うことで気分転換にもなります。
ちょっと体を動かすだけで、体の巡りがよくなって、気持ちまで軽くなる。この手軽さ、もっと多くの人に体感してほしいです。
3. 本当の「休息」を取り戻そう
3-1. 疲れの正体は“脳と心”にある
疲労の原因は複雑で重層的
最近の疲れって、昔みたいに「今日は肉体労働でクタクタ!」という単純なものじゃないですよね。私も以前は、「寝れば治るでしょ」と思っていたんですが、全然スッキリしなくて。
疲れの正体って、実は“肉体”だけじゃなく、“脳”や“心”の中にも深く潜んでいるんです。
情報・感情・人間関係が無意識に消耗
スマホやSNS、仕事の人間関係、家族のこと…。頭の中が常にフル回転している感じで、いつの間にか心が摩耗しているんですよね。目には見えない疲れだからこそ、気づきにくく、放っておきがち。
休み方にも「質」が求められる時代
「寝たはずなのに、全然疲れが取れてない…」なんてこと、ありませんか? 現代では、“どう休むか”も大事なスキル。ただ横になってスマホいじるだけじゃ、休息とは言えないのが現実です。
3-2. “現代疲労”に効く3つの処方箋
情報を断ち、脳を「静か」にする時間を
正直、私も以前は寝る直前までスマホでニュースをチェックしたり、SNSを眺めたりしていました。でもそれが、脳をずっと働かせていた原因だったんです。
いわゆる「デジタルデトックス」。難しいことではなくて、スマホの電源を1時間だけ切って、音楽を聴くとか、ぼーっとするだけでも十分。
最初はソワソワしましたが、慣れてくると、脳が静かになる感覚がちゃんとわかります。
睡眠環境は「音・光・温度」の最適化を
「寝てるはずなのに眠りが浅い」って方、多いですよね。私もそうでした。
そこで取り入れたのが、遮光カーテンと寝室の温度管理。エアコンのタイマー設定を使って、寝入りにちょうどよい温度(夏なら26℃前後)を保つようにしたら、明らかに寝起きが違うんです。
さらに、耳栓やホワイトノイズアプリも使って、音のストレスをカット。
小さな変化でも、睡眠の質って一気に上がるんですよ。
「人と比べない」マインド習慣を持つ
これが一番難しかったかもしれません。SNSで他人の生活が目に入るたびに、「自分は頑張りが足りないのかな」って思ってしまって…。
でも、他人は他人、自分は自分ってちゃんと線を引くように意識すると、心がだいぶ軽くなりました。
「今日の自分、よくやった」と一日一回でも認めてあげるだけで、心の疲れ方がまったく違います。
3-3. 今日から始める“小さな変化”
スマホの使用時間を1日30分減らす
いきなり「スマホ断ち」は無理でも、「1日30分だけ減らす」ならどうでしょう?
私の場合、まずはiPhoneのスクリーンタイム機能で自分の使用時間をチェックすることから始めました。
そこから、SNSを開く時間を“夜8時まで”と決めるだけでも、脳の疲れがだいぶ軽く感じるように。
ルールをゆるく設けて、少しずつでも意識できればOKです。
就寝前1時間は「何もしない時間」を持つ
この“無刺激時間”は、私の中では革命でした。
湯船にゆっくりつかって、スマホは触らず、好きな音楽を流して、あとはストレッチを少し。
最初は「ヒマすぎる!」と思ってましたが、3日もすれば逆にこの時間が楽しみに。
睡眠の質も改善されて、翌朝のダルさが全然違うんです。
朝の10分ウォーキングを習慣にする
朝のウォーキング、舐めてました。たった10分でも、朝日を浴びながら体を動かすと、気持ちが前向きになるんですよね。
私は通勤前に駅の一つ手前で降りて歩くようにしています。
ちょっと面倒だなと思う日もありますが、その分、一日をポジティブに始められるんです。
次の休みの日に思いっきり寝だめするよりも、日々の小さな習慣が“本当の休息”をつくってくれる——そう実感しています。
疲れの正体を知って、自分に合った休み方、ぜひ見つけてくださいね。