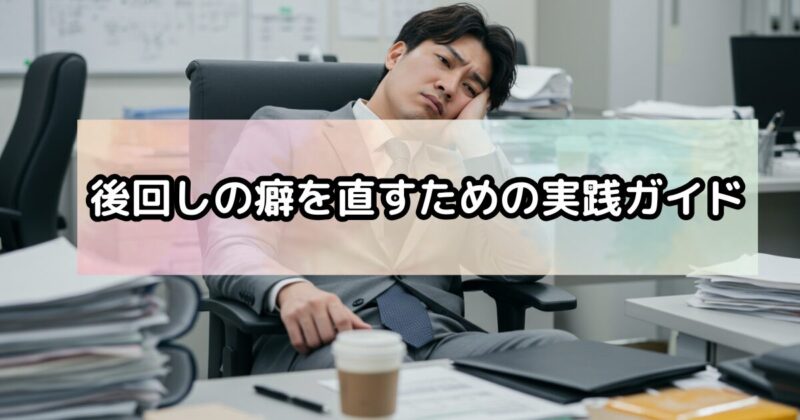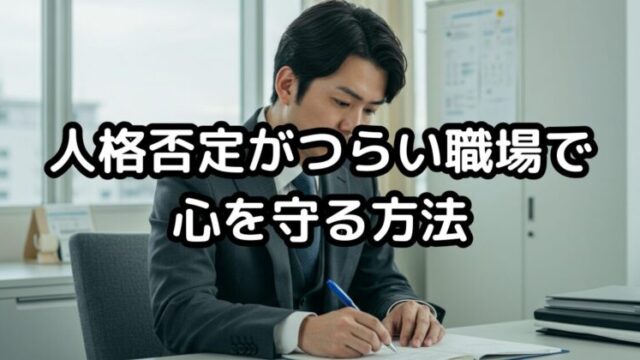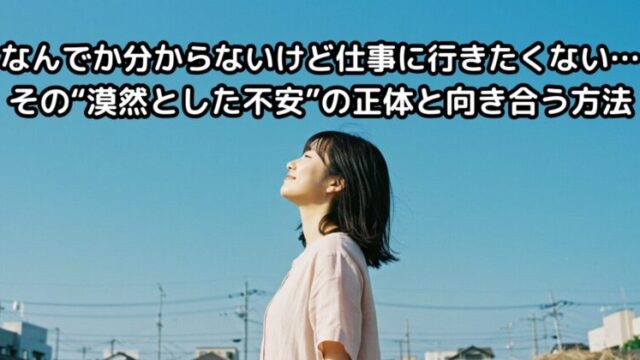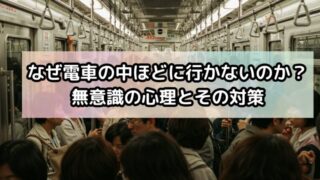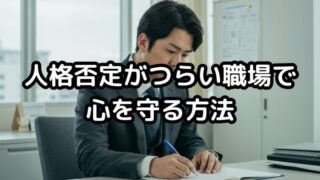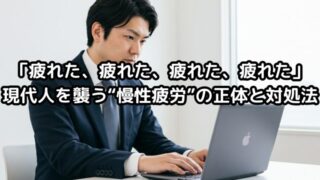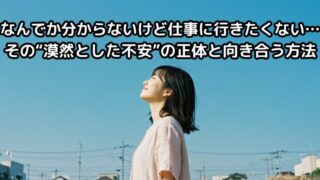1.後回しの癖が日常をむしばむ理由
1-1.身近にある「後回しの癖」
「やらなきゃいけない」と思っているのに、なぜか手をつけられない。そんな後回しの癖に心当たりのある方は多いのではないでしょうか。日常の中でつい先送りしてしまう行動には、実は共通する理由があります。
書類の提出をギリギリまで放置してしまう
仕事で「この書類、今週中に出しておいてくださいね」と言われて、「わかりました!」と返事したのに、気づいたら金曜の夕方。そんな経験、誰にでもあると思います。頭では「早めにやっておこう」と思っていても、なかなか行動に移せない。後回しの癖は、ビジネスシーンでも日常茶飯事です。
掃除や片付けがつい後回しになる
部屋の隅にたまったホコリ、洗面所の水アカ…。見て見ぬふりをしているうちに、どんどん後回しになっていませんか?掃除や片付けって、やるとスッキリするのに、どうしても「今じゃなくていいか」と思ってしまう。これも後回しの癖が原因です。
タスクを先送りして自己嫌悪に
「今日こそやろう」と思ったタスクを、また後回しにしてしまった…。そのたびに自己嫌悪に陥る。そんな負のループに入ると、やる気もなくなってしまいます。後回しの癖は、気づかぬうちに自分の自己評価を下げてしまうのです。
1-2.なぜ後回しは改善されにくいのか?
意志の弱さだけで片付けられてきた問題
「後回しにするのは意志が弱いから」――昔からよく聞く言葉です。でも、それだけで片付けてしまっていいのでしょうか?実際には、意志の強さだけで解決できるほど簡単な問題ではないのが現実です。根性論だけでは、この癖はなかなか直りません。
後回しは「習慣」や「環境」に根づいている
後回しは、単なる性格の問題ではなく、毎日の習慣や置かれた環境と密接に関係しています。たとえば、テレビやスマホなど気を散らすものが身近にあると、ついそっちに流れてしまう。後回しは、日常の中にある仕組みの問題でもあるのです。
癖の根本改善に必要なのは「構造の理解」
後回しの癖を本当に改善するためには、「なぜ後回しにしてしまうのか」という構造を理解する必要があります。行動だけを変えようとしても、根本にある考え方や環境がそのままだと、また同じことの繰り返しになってしまいます。
2.後回しの癖を読み解く
2-1.後回しの癖とは何か?
後回しは「選択の先送り」である
「後回しの癖」とは、やるべきことを意識しながらも、意図的に今はやらないという選択を繰り返してしまう状態のことです。実はこの癖の本質は「意思決定の先送り」にあります。今決断するのが面倒、エネルギーが足りない、失敗が怖い。そういった心理が、選ぶこと自体を後回しにさせているのです。
癖として定着する過程
「まぁ、今日はやらなくてもいいか」「明日こそやろう」…こんな小さな後回しが、習慣化していきます。行動パターンが繰り返されると、それは無意識の癖になります。そしてその癖は、日常のあらゆる場面で私たちの行動を止めてしまう存在になっていきます。
脳の仕組みから見た後回し
脳には「すぐに得られる報酬を優先したい」という性質があります。これを「現在バイアス」と呼びます。たとえば「掃除するよりスマホを見る方が楽」と感じるのは、まさにこのバイアスのせい。後回しの癖は、脳の構造に根づいた自然な反応とも言えるのです。
2-2.後回しの癖を引き起こす要因
自己効力感の低下
「どうせやってもうまくいかない」「途中で挫折しそう」——こうした思い込みは、自己効力感の低下によるものです。自信が持てないと、タスクに向かう意欲が薄れてしまい、後回しの癖が強まります。実際、厚生労働省の調査でも、自己効力感が行動の持続に影響を与えることが示されています。
タスクの不明確さ
やるべきことが曖昧だと、人はなかなか動き出せません。たとえば「資料を作る」というタスクでも、具体的に「誰に向けて、何を、いつまでに作るのか」がはっきりしていないと、後回しにしてしまいがちです。明確でないタスクは、脳にとって「見えない敵」と同じです。
マルチタスク環境での集中力の低下
現代の職場や家庭では、スマホ通知、複数の仕事、家庭の用事…と、同時にいくつもの刺激に囲まれています。このマルチタスク環境が集中力を削ぎ、結果として「あとでやろう」を助長してしまいます。後回しの癖がつく背景には、環境による影響も大きく関わっているのです。
2-3.後回しの癖を改善する方法
タスクを「見える化」する
やるべきことを目に見える形にすることは、後回しの癖を断ち切る第一歩です。たとえばホワイトボードや付箋、スマホのアプリなどを使って、タスクを一覧化する。NRIの生活者調査2023年でも、「視覚化された予定は実行率が高くなる」とのデータがあります。自分の「やること」が見えると、行動に移すきっかけが生まれます。
スモールステップの習慣化
いきなり完璧を目指すのではなく、「5分だけ掃除」「1項目だけ資料作成」といった小さな一歩を習慣にすることで、後回しの癖を緩和できます。成功体験を重ねることで、脳は「やったほうが気持ちいい」と学習し、行動が前向きになります。
ご褒美でモチベーションを維持する
タスクを終えた後に「自分にご褒美」を用意するのも、効果的です。好きなお菓子、動画鑑賞、コーヒータイムなど、小さな報酬があるだけで「今やろう」という気持ちがわいてきます。後回しの癖を打破するには、脳が喜ぶ仕組みづくりが鍵です。
関連リンク(外部):
ハーバード大学:Visible Thinking「自身の思考プロセスを明確にし、理解を深めるための手法」(英語)
3.後回しの癖を明日から変えるには
3-1.後回しの癖は変えられる
後回しは意志の問題ではない
「なんで自分はこんなに後回しにしてしまうんだろう」と悩む方、多いと思います。でも実は、これは単なる“意志の弱さ”の問題ではありません。
脳の報酬系や、集中力を妨げる環境が、後回しの癖を自然に作り出してしまっていることが多いんです。だからこそ、自分を責める必要はまったくありません。
原因を知れば対処できる
原因がわかれば、対応策も見えてきます。たとえば「やることが曖昧だと後回しにしやすい」と知っていれば、最初にやることを具体的に書き出すことで防げます。
癖は見える形にすることで、だんだん距離を取れるようになります。自分の行動を少し俯瞰して見ること、それが変化のスタートです。
癖の改善には小さな実践が重要
後回しの癖を改善するには、一気に変えようとせず、小さな行動を積み重ねることが大切です。「1日5分だけやってみる」「まずは1つだけ片付ける」。
こうした無理のないステップが、習慣づくりにつながります。日々の実践が、未来の行動を変えていきます。
3-2.後回しの癖に効く対処法
タスク管理アプリの活用
タスクを頭の中だけで整理しようとすると、どうしても後回しになりがちです。そんな時に便利なのが、タスク管理アプリ。「Todoist」や「Notion」は、予定やタスクを見える化しやすいツールとして人気があります。
視覚的にやることが整理されることで、「今、何をやればいいか」が明確になります。
1日5分ルールの導入
「とりあえず5分だけやってみる」というルールは、後回しの癖を打ち破るのにとても効果的です。5分やれば意外と続くし、「始める」こと自体のハードルがグッと下がります。
心理的な抵抗を下げることで、自然と行動に移りやすくなります。
生活リズムの見直し
どんなにやる気があっても、疲れている時間帯にタスクを入れてしまうと後回しになりやすいです。
自分が集中しやすい時間帯に重要なことを済ませる工夫をするだけでも、後回しの頻度はグッと下がります。朝型か夜型か、自分のリズムを見直すことは意外と大切です。
3-3.後回しにしないためにどうすればいいか
タスクを紙に書き出して1つだけ実行する
私がまずやるなら、ノートに今日やるべきことを全て書き出します。そしてその中から「これだけは」という1つを選びます。
完璧にこなす必要はありません。まずは「やる」「終わらせる」という小さな成功体験を作ることが目的です。
1週間、後回しメモを取る
次に、1週間だけ「何を後回しにしたか」をメモしてみます。パソコンでも紙でもOKです。どんな場面で、どんな理由で先送りしたのかが見えてきます。
可視化することで、自分の傾向がわかり、対策も立てやすくなります。
後回しにしたくなる時の気持ちを書き出す
最後に、後回しにしそうになったときの気持ちをメモします。「なんとなく面倒だった」「不安だった」など、感情に気づくことはとても大切です。
後回しの癖は、感情と深くつながっていることが多いからです。この気づきが、癖を変えるための第一歩になります。
関連リンク(内部):
なんでか分からないけど仕事に行きたくない…その“漠然とした不安”の正体と向き合う方法