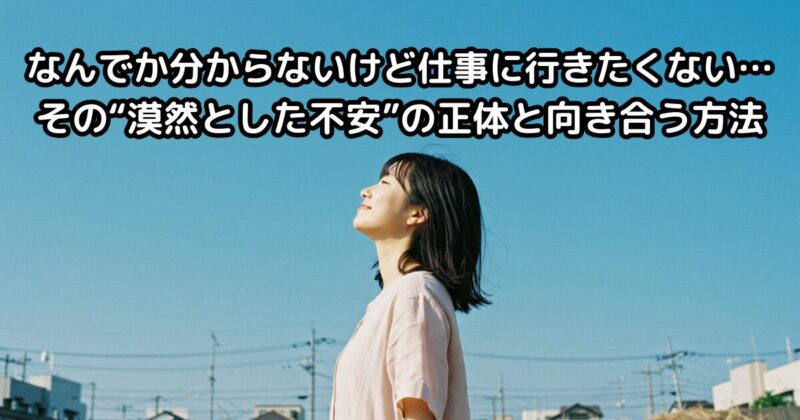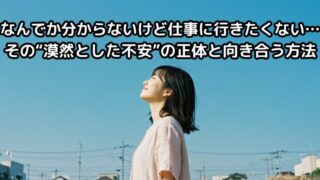1. その“なんとなく不安”が、あなたを動けなくしている
1-1. 朝になると、理由もなくつらい日
出勤前の「ため息」が習慣になっている
正直に言うと、ここ最近、朝起きて出勤する前に必ず深いため息をついている自分がいます。
別に職場で何かトラブルがあったわけでもないし、人間関係がすごく悪いというわけでもありません。でも、なぜか体が重くて、心もどこか沈んでいて……。
朝ごはんを食べて、身支度を整えて、いざ家を出ようとするその瞬間。「あー、行きたくないな…」って、声には出さないけれど、心の中でははっきりそう思っています。
以前の私は、仕事がつらい日はたしかにあったけど、それでも理由がはっきりしてたんです。「あの会議が嫌だな」とか、「あの上司に会いたくないな」とか。でも、今は違う。ただ“なんとなく”行きたくない。自分でもよく分からないんです。
そして、そんな自分に対して、「こんなことでしんどくなるなんて、自分ってダメだな」って、さらに落ち込んでしまう。悪循環ですよね。
同じような感覚を味わっている方、いらっしゃいませんか?
休日は元気なのに、月曜が怖くなる
土曜日や日曜日になると、友達と出かけたり、趣味に没頭したりして普通に楽しめてるんですよ。笑って過ごせるし、ごはんも美味しく感じる。
でも、日曜の夜あたりから、胸のあたりがモヤモヤしてくるんです。寝る前になると、翌朝のことが頭をよぎって、急に心がざわざわ。眠れなかったり、眠れても朝はぐったり。
「また一週間が始まるのか」って考えるだけで、心がギュッと縮こまるような感覚。
たとえ明確な予定がない月曜でも、「仕事に行く」というだけで、気持ちが重くなるんですよね。
「やめたい」とまでは思わないが…
とはいえ、仕事をやめたいわけではないんです。やりがいを感じる瞬間もあるし、チームの人たちとも普通に会話できます。
でも、毎日が少しずつ「しんどい」の積み重ねで。朝になるたび、「今日もなんとなく憂うつだな」って思ってしまう。
自分でもはっきり理由が分からないからこそ、どう対処していいのかも分からない。だれにも相談しづらくて、ますます一人で抱え込んでしまう。
こういう感覚、実は意外と多くの人が経験してるって知ってましたか? 次は、なぜ私たちが「漠然とした不安」に悩まされるのか、その背景を一緒に考えてみたいと思います。
1-2. なぜ人は“漠然とした不安”に悩まされるのか
社会的には“普通”でも感じる不調
私自身、周りから見たら「何の問題もない人」に見えるかもしれません。会社にもちゃんと行ってるし、遅刻もしていない。成果もそれなりに出している。
でも、そういう「外から見た普通さ」と、自分の内側で感じている「しんどさ」って、ぜんぜん一致しないことがあります。
それが、「自分だけおかしいのかも」と思わせる原因にもなってしまうんです。
「やる気の低下」とは違う心の重さ
やる気がないとか、怠けたいわけじゃないんです。むしろ「ちゃんとしなきゃ」と思ってる。
でも、心のどこかが重たくて、どうしても動けない。そんなふうに、自分の気持ちを言語化できないまま過ごしている人、多いんじゃないでしょうか。
これは「サボりたい」わけでも「燃え尽きた」わけでもない。もっと曖昧で、説明しにくい不安なんですよね。
「甘え」と片づけられてきた背景
昔はよく「気の持ちようでしょ」とか「根性が足りないんじゃない?」なんて言われる時代でした。
今でこそ、メンタルヘルスの大切さは少しずつ認知されてきたけど、それでもまだ「弱音を吐く=甘え」と感じてしまう風潮、ありますよね。
だからこそ、「漠然とした不安」を言葉にすること自体が難しくて、心の中に抱え込み続けてしまう。
でも大丈夫。次の章では、その“正体のない不安”がどうして起きるのか、そしてどう向き合えばいいのかを、私の体験も交えながら詳しくお話ししていきます。
2. その不安はどこから来るのか、どう向き合えばいいのか
2-1. 漠然とした不安とは何か?
正体のない「情動ストレス」による心の疲れ
「なんかモヤモヤする」「なんでか分からないけど気が重い」——そう感じるとき、実は私たちは“情動ストレス”という心の負荷を抱えていることがあります。
私も以前、「原因不明の不安」に悩まされたことがありました。仕事自体は順調、トラブルもないのに、朝になるとどうしても足が向かない。今思えば、心の奥でずっと小さなストレスが積み重なっていたんですよね。
この“情動ストレス”って、明確な出来事がなくても生まれるんです。たとえば「なんとなく緊張」「うまく言葉にできない心配ごと」など。目に見えないからやっかいで、自覚しにくいのも特徴です。
情報過多と感情の処理不足が影響
最近はスマホひとつで大量の情報が手に入りますよね。SNSやニュース、動画など、ずっと刺激を受け続けている状態です。
私もよく、通勤中に何気なくSNSを見ていたら、他人の成功談や充実した日常に触れて、知らず知らずのうちに自分を比べて落ち込んでしまったりしていました。
この「他人との比較」は自分でも気づかないうちにストレスになり、処理しきれない感情が積もっていきます。それが、“漠然とした不安”につながってしまうんです。
いわゆる「感情の渋滞」状態。心のキャパがパンパンなのに、休ませるタイミングがない。それでは、どんどん動けなくなって当然ですよね。
脳のエネルギー切れが招く無気力状態
あまり知られていませんが、実は「脳」ってすごくエネルギーを使う臓器なんです。考えるだけでも、かなりのパワーを消費します。
心理学では「認知資源(Cognitive resources)」という言葉があります。これは“集中力や判断力のエネルギー源”のようなもので、これが枯渇すると、物事に対してやる気が出なかったり、感情が鈍くなったりします。
私も、仕事で気を張っている日が続いたときは、家に帰って何も考えられなくなることがありました。「疲れた」とすら思えないほど無気力になる感じです。
これもまた、漠然とした不安の原因のひとつ。体は元気でも、脳が疲れてしまっている。そんな状態では、どんな仕事でも「行きたくない…」と感じるのも自然なことなのかもしれません。
2-2. なぜ今、不安が増えているのか
厚労省調査でも、働く人の6割がストレスを実感
【出典】厚生労働省「労働安全衛生調査(令和4年)」
令和4年に発表された厚生労働省の調査では、働く人の実に約6割が「強いストレスを感じている」と回答しています。ストレスの内容は、仕事の量・人間関係・将来への不安など多岐にわたります。
つまり、「私だけがしんどいんじゃない」と言えるデータがあるということです。
私自身、「みんな普通に働いているのに、なんで自分だけ…?」と責めてしまうことがありました。でも、実は多くの人が同じように心にストレスを抱えていたんですよね。
働き方の変化で「孤独感」が強まっている
ここ数年で、リモートワークやフリーアドレス制度など、働き方が大きく変わりました。一見、自由度が高まったように見えますが、その反面「人との関わり」がぐっと減っています。
私の周りでも、「在宅勤務は楽だけど、誰とも雑談しない日があると気分が沈む」と言う人が増えました。仕事の悩みを話す相手がいない。ちょっとした愚痴も言えない。
そうなると、「ひとりで抱え込む」ことが当たり前になり、漠然とした不安がどんどん膨らんでしまうんです。
人は、ほんの少しの共感や言葉のやりとりでも安心できます。逆に、それがまったくないと、心の中に空洞ができてしまうんですよね。
成果主義や将来不安が心の余裕を奪う
今の社会は、「結果を出すこと」が重視されがちです。成果主義やKPI、数字での評価…。努力しても、それが評価につながるとは限らない世界です。
さらに、年金問題や物価上昇、将来の雇用への不安など、先の見えない状況が続いています。
私もふとした瞬間に、「このままで大丈夫かな?」「10年後、自分はどうしているんだろう」と考えて不安に襲われることがあります。
そうした“未来への漠然とした恐れ”が、目の前の仕事にまで影を落とすことがあるんですよね。
このように、私たちが感じている漠然とした不安には、実は社会的な背景がしっかりとあるのです。
2-3. 漠然とした不安とどう向き合えばいい?
感情を書き出して「可視化」する
まずおすすめしたいのが、「感情を書き出す」ことです。これは「ジャーナリング」と呼ばれる方法で、思っていることを言葉にするだけで、心が少しスッキリします。
私もノートを1冊用意して、朝や寝る前に「今どんな気分か」「何が気になっているか」をざっくり書き出しています。
書き方は自由です。箇条書きでも、日記風でもOK。「なんとなくモヤモヤする」が、「あの発言が引っかかってるのかも」と見えてくることがあります。
小さな成功体験で「安心感」を積む
大きな変化を求めなくても大丈夫。むしろ、日常の中で小さな「やれたこと」を積み重ねることが大切です。
私は「今日は朝きちんと起きられた」「夕飯をちゃんと作った」など、どんなに小さなことでも手帳に書き残すようにしています。
これが意外と効きます。「今日もちゃんとやれてる」という安心感が、少しずつ自信になっていくんです。
専門家や外部支援を頼ることも選択肢
そしてもう一つ大事なこと。一人で抱え込まないことです。
最近は、企業に産業医やカウンセラーが常駐していることも増えています。匿名で相談できるチャットサービスや、電話相談窓口もあります。
「相談するなんて大げさかな…」と思っていた私ですが、実際に話してみると「気持ちを整理するってこういうことなんだ」と実感しました。
心が疲れているときは、体と同じように“専門のケア”が必要なんですよね。頼ることは、決して弱さじゃないと思います。
3. 見えない不安に振り回されず、自分を守る
3-1. あなたの不安は「理由がない」からこそ本物
漠然とした不安は多くの人が抱えている
「なんとなく仕事に行きたくない」。
この感情、実はとても多くの人が抱えているものなんです。
私も何度もそう感じてきましたし、職場の仲間も「理由はわからないけど、今朝は重かった」と話すことがあります。
つまり、あなたが特別なんじゃなくて、それは“人として自然な反応”なんですよね。
正体がなくても、対応策は存在する
不安の原因が見えにくいと、「どうすればいいのか分からない」と感じてしまいますよね。
でも、そんなときでもできることはあるんです。小さな行動や習慣の積み重ねで、少しずつ気持ちは整っていきます。
「対処できる」と思えるだけで、心がスッと軽くなる瞬間もありますよ。
自分を責めず、少しずつ整えていこう
ここで一番伝えたいのは、「自分を責めなくていい」ということ。
何もできない日があってもいいし、気持ちが沈んでいる日は、無理に元気に振る舞わなくても大丈夫。
まずは、「そういう日もある」と自分にOKを出してあげることが、回復の第一歩になります。
3-2. 心が軽くなるおすすめツールとサービス
メンタルケアの決定版アプリ【Awarefy】
「これはいい!」と思ったのが、Awarefyというアプリです。
毎日、気分を簡単に記録するだけで、自分の感情の波が見えてくるんです。
日々の感情や思考を記録しながら、マインドフルネスや自己理解を深めることができる習慣化サポートアプリです。気分の波やストレスの原因を「見える化」し、心のモヤモヤを整理する手助けをしてくれます。
3-3. まずは今日を「やりすごす」
今日やることを「1つ」に絞ってみる
私が一番効果を感じた方法は、「今日やることを1つに絞る」ことでした。
以前は、「全部完璧にやらなきゃ」と思い込んで空回りしてばかり。でも、ある日「今日はメール返信だけできればOK」と決めてみたんです。
結果、不思議なことに「その1つだけ」なら集中できて、それが達成感につながりました。
小さな“やれた感”が、次の動きへの原動力になるんです。
SNSやニュースを1日だけシャットアウト
もうひとつ試してよかったのが、「情報を遮断する日」を作ること。
私は1日だけスマホのSNSとニュースアプリを全部オフにして、静かな時間を過ごしてみました。
最初は手持ち無沙汰だったけど、次第に「気が散っていたんだな」と気づけました。
外からの情報って、無意識にストレスになってるんですよね。
「自分の中の声」を聞くには、いったん外部を遮断する時間も必要だと実感しました。
信頼できる人に「言葉にして話す」
そして最後に。やっぱり、誰かに言葉で話すことって大切です。
私は、ずっと言えなかったことを、思い切って友人に打ち明けたとき、「それ、私も感じてたよ」と言われてホッとしました。
話すことで、不安の“輪郭”が見えてくるんですよね。曖昧だった気持ちに、ちょっとずつ名前がついていく感覚。
もちろん、身近に相談相手がいなければ、オンライン相談でも大丈夫。
声に出すこと、それ自体が自分を助ける行動なんです。
焦らなくてもいい。今日は「やりすごす」でいい。
そう思えるだけで、少しだけ心が軽くなるはずです。